iDeCoとは
老後に特化した積立制度。(投資信託などを活用)
iDeCo活用のメリットは大きく分けて2つ運用益への税金優遇制度・節税効果になります。本記事ではどのぐらいの効果があるのか、メリットや注意点について解説していきます。
節税効果について
年収500万をモデルに節税効果についてシミュレーションしていきます。
iDeCoなし
給与収入:500万 給与所得控除:144万 社会保険料控除:75万 基礎控除:48万(43万) 所得税:約13万 住民税:約24 万
iDeCoあり
給与収入:500万 給与所得控除:144万 社会保険料控除:75万 基礎控除:48万(43万) iDeCo:27,6万(1ヶ月23,000円) 所得税:約11万 住民税:約21万 節税効果:5万←1年間当たりの効果。(10年、20年・・と長期による効果も大きい。)
税金優遇制度について
iDeCoを活用することでの税金優遇制度をみていきます。ちなみに運用期間中は非課税ですので、受取時の効果を一般金融商品と比較しながら見ていきましょう。
一般金融商品の場合(株、投資信託、銀行預金など)
投資金額:1,000万 受取金額:2,000万 運用益:1,000万 税金:200万(税率20.315%)※源泉徴収の場合。確定申告される場合は変わる可能性あり。
iDeCoの場合
一時金で受け取る場合 投資金額:1,000万 受取金額:2,000万 運用益:1,000万 退職所得控除:①20年勤続(800万)②30年勤続(1,500万)を運用益から差引、残った金額に税率を掛ける。※自分の勤続年数によって変わります。 税金①:1,000万ー800万=200万÷2=100万×税率=約15万(所得税と住民税合わせて) 税金②:1,000万ー1,500万=0(非課税)
iDeCoを活用していない場合とで支払う税金がここまで大きく変わります。増えた以上に払うことはないですが、長期での資産形成を考えると、活用したい仕組みになります。
ちなみに年金で受け取る場合には、その年に受け取る老齢年金や個人年金保険等と合算したうえで税率が決まります。iDeCo以外の退職金がある場合には、それも含めて計算の必要性があります。
メリット
メリットはここまで解説してきた上記2つの制度です。
デメリット
これだけ良い制度なので、iDeCoのデメリットは?と聞かれることが多いですが、デメリットというよりは、注意点の方が個人的にしっくりきますので、いくつか紹介しておきます。代表的な60歳まで現金を引き出せない。投資対象によっては、運用益がマイナスになることも。節税されている金額を把握しておくことで、節税されている金額を投資や積立に回すことや、旅行や習い事などの別の経験に使うなど。。。
まとめ
ここまでiDeCoについて節税、受取時の税金優遇の部分を解説してきました。とてもメリットが多い仕組みですが、家計や今後の人生設計次第ではデメリット部分が大きくなってしまいます。本人の目的にとって合う仕組みかどうか?ここが一番重要かと思います。老後の年金が少ない方にとっては、自分の老後への仕送り。と考えると、節税しつつ、運用も出来てしまう素晴らしい仕組みですが、今しか出来ない経験(事)に使う事が出来ない。という面もありますので、ご自身、家族と将来について話し合いをしたうえで、この仕組みを検討されてはいかがでしょうか?


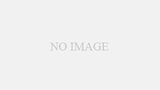
コメント